ヤンセン “つながる” プロジェクト
市民公開講座
『ともに学ぼう、病気や治療との向き合い方』ワークショップ開催レポート
開催場所:JPタワー ホール&カンファレンス
開催日時:2023年9月24日(日)14時~15時半
登壇者:新潟薬科大学医療技術学部血液学教授 青木定夫先生
CLL(慢性リンパ性白血病)患者・家族の会代表 齊藤治夫さん
全日本川柳協会常任幹事 藤井敬三さん
「ヤンセン “つながる” プロジェクト『ともに学ぼう、病気や治療との向き合い方』ワークショップ」は、患者さんにご自身の病気・治療について正しい知識を学んでいただき、病気・治療に主体的に向き合う姿勢を身につけることで、医療者と積極的に相談ができるようになることを目指しています。また、患者さんやそのご家族が、病気・治療に対する想いや気持ちを「川柳」を通じて共有することで、“つながる場“をご提供することを目的としています。このプロジェクトを通じて、”患者さん”と、病気や治療との向き合うために必要な”情報”がつながる、そして、患者さんの”気持ち”と”気持ち”がつながること、をコンセプトとしています。
第1回「ともに学ぼう、病気や治療との向き合い方」ワークショップ
2023年9月24日に開催された「ヤンセン “つながる” プロジェクト『ともに学ぼう、病気や治療との向き合い方』ワークショップ」では、まず患者さんに病気・治療について正しい知識を学んでいただくため、新潟薬科大学医療技術学部血液学教授の青木定夫先生から慢性リンパ性白血病(CLL)/小リンパ球性リンパ腫(SLL)、マントル細胞リンパ腫(MCL)、原発性マクログロブリン血症(WM)/リンパ形質細胞性リンパ腫(LPL)の基礎情報について、ご講演いただきました。講演の後、CLL(慢性リンパ性白血病)患者・家族の会代表齊藤治夫さんをお招きしたパネルディスカッションと、全日本川柳協会常任幹事の藤井敬三さんをお招きした川柳ワークショップを実施しました。
講演
新潟薬科大学 医療技術学部 血液学 教授
青木定夫 先生

慢性リンパ性白血病(CLL)とCLL
慢性リンパ性白血病(CLL)は、白血球の一種であるリンパ球ががん化する悪性リンパ腫の一病型です。がん化したB細胞(Bリンパ球)の形態が似ているマントル細胞リンパ腫(MCL)、原発性マクログロブリン血症(WM)/リンパ形質細胞性リンパ腫(LPL)を「CLL 類縁疾患」と呼びます。
国内の年間10万人当たりの有病率はCLLが2.55人、MCLが2.09人、LPLが0.28人です。
CLL及びCLL類縁疾患は細胞の形態が類似しているものの、治療方針や予後が異なります。一般的には白血球表面の糖タンパク質である「CD(cluster of differentiation)」を指標に診断しますが、非典型例もあるため確定診断の難易度が高いのが現実です。
慢性リンパ性白血病(CLL)/小リンパ球性リンパ腫(SLL)とは
慢性リンパ性白血病(CLL)は、血液のがんの一つで、CLL細胞というがん細胞が血中や骨髄で増殖します。 同様にがん細胞がリンパ節組織で増えている場合には、小リンパ球性リンパ腫(SLL)と呼ばれます。慢性リンパ性白血病(CLL) も小リンパ球性リンパ腫(SLL)も患者さんの多くは70歳前後です。日本の患者さん数は欧米の10分の1ほどで、発症の原因は不明ですが、遺伝的要因が大きいのではないかと考えられています。
無症状期は治療を行わない経過観察(watch and wait)となり 、経過観察中は、定期受診とともに一般的な健康診断の受診、またこれまでなかった症状がある場合は、主治医に相談することが推奨されます。
全身倦怠感、発熱、体重減少等の症状やリンパ球が急に増えるなどCLL/SLLの活動性がみられた場合には、治療が開始となります。
マントル細胞リンパ腫(MCL)とは
マントル細胞リンパ腫(MCL)は、リンパ節のマントル帯に由来する異常なBリンパ球が増加する、血液のがんの一つです。発症時の年齢の中央値は60歳代半ばで男性に多いとされています。
典型的な症状はリンパ節の腫れで、発熱、盗汗(大量の寝汗)、体重減少などの全身症状も特徴的です。さらに一部では骨髄浸潤による貧血や出血、脾臓の腫れなどの症状を呈します。
MCLはCLL類縁疾患の中でも進行が早く、多くの患者さんは確定診断後に速やかに治療が開始されます。MCLは標準治療が確立しておらず 年齢や検査結果に応じて治療方針が異なりますが、がんを抑制する特定の遺伝子に変異がある場合は、早期の強力な治療が薦められています。ただし、MCLの一部は緩やかな経過をたどり、無治療経過観察も選択肢となります。
リンパ形質細胞性リンパ腫(LPL)/原発性マクログロブリン血症(WM)とは
リンパ形質細胞性リンパ腫(LPL)は、CLLで認められる小型成熟リンパ球に加え、Bリンパ球が分化してできた形質細胞が混在する点が特徴です。発症の年齢の中央値は71歳で、男性にやや多いと報告されています。
LPL患者さんの90-95%を占める 、がん細胞がつくる異常なIgMの増加例は、特に原発性マクログロブリン血症(WM)と分類します。
患者さんの約4分の1は無症状で、有症状の場合も倦怠感や貧血症状など非特異症状が多く、場合によっては血小板減少などが認められます 。また、IgMの増加により血流が悪化する、過粘調度症候群を起こすことがあります。
無症状期は経過観察(watch and wait)となり、症状や合併症が認められた場合に治療を開始します。標準治療は確立されておらず、患者さん毎に治療方針を主治医と検討して決めていく必要があります。
参考文献
1) Dai Chihara, et al. Br J Haematol. 164: 536–545,2014
2) 日本血液学会編: 造血器腫瘍診療ガイドライン 2023年版,金原出版, 2023.
3) Morie A. Gertz: Am J Hematol. 98: 348–358,2023
パネルディスカッション
講演後は、新潟薬科大学医療技術学部血液学教授の青木定夫先生とCLL(慢性リンパ性白血病)患者・家族の会代表の齊藤治夫さんによる、「治療開始前の病気との向き合い方」、「治療開始後の病気や治療との向き合い方」、「病気・治療に主体的に向き合うためのアドバイス」の3つをテーマとしたパネルディスカッションが行われました。
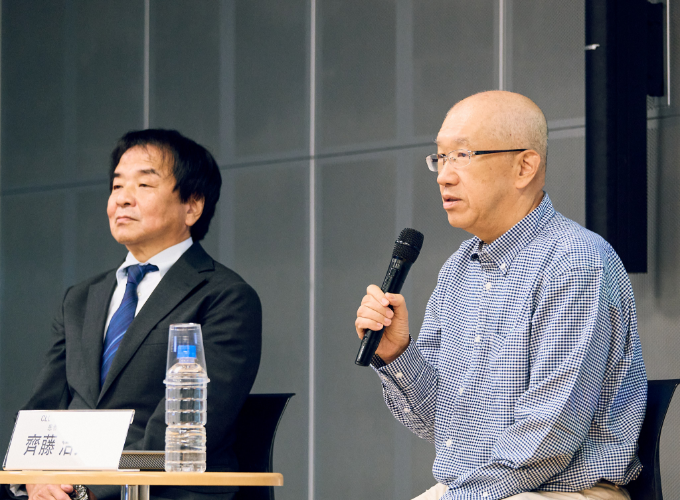
テーマ①治療開始前の病気との向き合い方
- Q. 治療開始前の無治療経過観察=watch & waitの期間とは、具体的にどのような期間となるのでしょうか。
- (青木先生)CLL及びCLL類縁疾患では、無症状期に治療をすることは患者さんにとって利益より不利益が多いという医学的研究結果に基づき、無治療経過観察期間が存在します。病気なのに治療をしないことを患者さんは不安に感じるかもしれないですが、むしろ「病気として質が悪くない」くらいに受け止めていただけるとよいと思います。
- Q. 齊藤さんご自身は、watch & waitの期間はございましたか。また、どのようなお気持ちでいらっしゃいましたか。
- (齊藤さん)私の場合はCLLの確定診断から2年間、経過観察となりました。最初に主治医から「すぐに治療をしなくても良い」と言われたときは、「早期発見、早期治療じゃないの?」と疑問に感じました。診断を受けた病院では私が初のCLL患者だったため、より実績のある病院に行った方が良いのでは?とかなり慌てたことを覚えています。
- Q.治療開始前の患者さんは、ご自身の病気への向き合い方という点で、どのようなことを心がけるとよいのでしょうか。
- (青木先生)これらの病気は概して長期的な治療・管理が必要なため、主治医から告げられた診断・治療方針に疑問点があれば、患者さんは納得するまで主治医に尋ねることが最良の不安軽減策です。最近はインターネットの影響で、患者さんが玉石混交な大量の情報を得て、逆に不安が募ってしまう場合もあります。そのため、私は患者さんには患者・家族の会や製薬企業の患者さん向けのホームページなどでの情報収集を推奨しています。
テーマ②治療開始後の病気や治療との向き合い方
- Q.一方で治療開始後には、患者さん自身はどのようなことを心がけるとよいのでしょうか。
- (青木先生)患者さんの中には、がん治療薬の副作用は怖いというイメージが先行している方も少なくありません。ただ、副作用は患者さんごとに異なり、一定の対処法もあります。中には治療開始後に体調の変化を感じ、こっそり服用を中止する患者さんもいますが、これは主治医の検査結果の解釈や治療方針の判断に悪影響があり、最終的には患者さんに不利益が生じる場合があります。
服用後に体調の変化を感じた際は、次回の診察を待たずに主治医に連絡をして正直に伝えていただきたいですし、患者会などにも躊躇せずに相談することが重要です。治療は「副作用との戦い」ではなく、「病気との戦い」と捉え直して欲しいですね。
- Q.治療開始後の患者さんがご自身の病気に正しく向き合うために、患者会としてどのようなアドバイスをしていますか。
- (齊藤さん)患者会では疾患名のCLLを逆手にとって、「C=コミュニケーション」「L=ラーニング(学ぶ)」「L=リスニング(聞く)」という行動指針を有しています。やはり主治医や患者仲間などの話に耳を傾け、自らが話してコミュニケーションをとることが正しい情報を得る重要な手段です。患者会ではオンラインで懇話会を行っており、そこで経験者の話を聞き、副作用の理解や主治医への相談方法を学ぶ患者さんも少なくありません。
テーマ③病気・治療に主体的に向き合うためのアドバイス
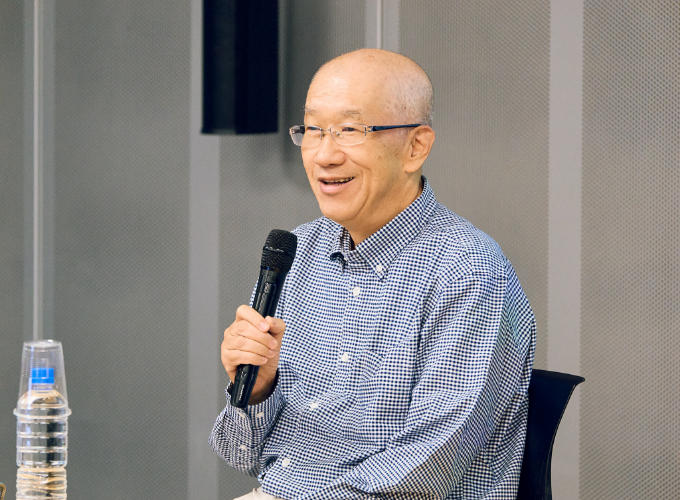
- Q.「患者力」向上のためのアドバイスやメッセージをお願いします。
- (青木先生)繰り返しにはなりますが、正しい情報と認識を持つことです。現在では患者さん向けの媒体やプログラム、相談窓口も用意され、より良い治療も確立されています。それらや主治医をうまく利用しながら、前向きに希望をもって治療に臨んで下さい。
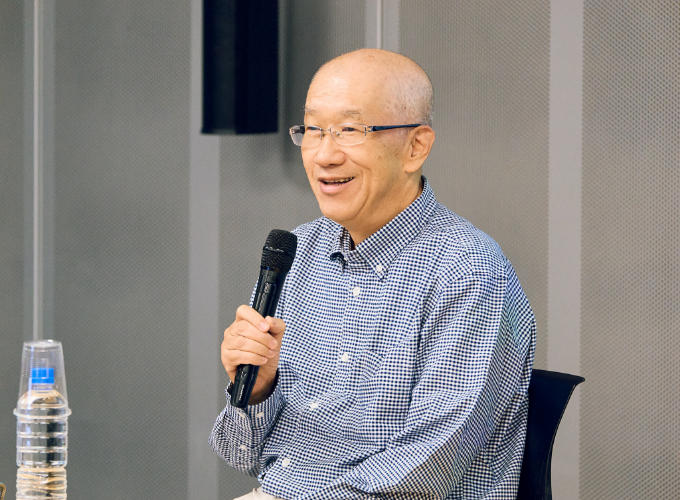
(齊藤さん)私たちの会では、患者さん向けセミナー、患者さん同士が悩みを話せるオンライン懇話会の開催、個別電話相談などを用意しているので、是非とも利用していただきたいです。また、通院先にある「がん相談支援センター」の利用もお勧めしています。自分自身の患者経験上、病気だけにとらわれず、やりがい、生きがい、働きがいという人生の目的を持ちながら、経過観察・治療の期間を過ごすことが大切だと思っています。
川柳ワークショップ

パネルディスカッションでは、患者さん自らが「悩みや不安を伝えることが重要」というお話がありましたが、ご自身のお気持ちを言葉にし難い方も少なくありません。そこでパネルディスカッションの後、全日本川柳協会常任幹事の藤井敬三さんもお招きし、川柳を通じて病気や治療に対する思いを共有する川柳ワークショップを行いました。
こちらでは、青木先生と斎藤さんに考えていただいた川柳を紹介します。
「海に降る 冷たい雨の 傘になる」(青木先生)
(青木先生)私の卒業した新潟大学医学部は、日本海に近く、秋から冬にかけて冷たい雨がみぞれ、雪に徐々に変化し、厳しい冬を迎えます。病気と診断された患者さんはまさに雨に降られたようなもの。医療者として少しでも濡れないよう、傘のような存在を目指したいという思いを込めました。
「質問を 準備すれども 忘れます」(齊藤さん)
(齊藤さん)CLLの確定診断後、何度も主治医への質問を考え、メモにして診察に向かいました。ところが診察時にはメモが手元に見当たらず、質問も思い出せず、主治医に「他に質問ありますか」と言われ、ついつい「大丈夫です」と言ってしまう自分を思い起こして川柳に表現しました。
ワークショップを終えて、斎藤さんからは「率直な気持ちを言葉で表すと、気持ちが楽になりますね」というお話がありました。また、青木先生からは「川柳という素晴らしい日本の伝統的な文化を介在させて、患者さんが普段医師にお話しにくい気持ちを聞かせていただくことは、素晴らしい試みだと思いました。皆さんの川柳を拝見して、患者さんのさまざまな困りごとに対するお手伝いをしていきたいという気持ちを新たにしました」というお話をいただきました。

